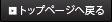-
下関青年会議所2024 > 理事長所信
理事長所信
はじめに
一人では乗り越えられない壁も、力を合わせることで乗り越えられる。それぞれの長所を活かし、短所を受け入れ合った先に、生み出せる世界がある。私たちが一人でできることには限界があり、みんなで協力しながらお互いを信じて何かを成そうとする中で、ひとり、またひとりと信頼できる人が増えていく。何かに本気で挑み、向き合うと、それがどのような結果となっても、自分に少し自信を持つことができる。自信がつけば、新しいことに挑戦するための一歩を踏み出しやすくなり、自分とは異なる考えを持った人を受け入れる度量も大きくなる。
まちにより良い変化を与えることができるのは、青年会議所である。1953年5月4日、28名の志高き青年により国内41番目の地域青年会議所として下関青年会議所が創設されてから70年。数多の先輩諸兄姉が、その思いを胸に、まちのため、地域の人のために、真剣にぶつかり合って議論し、まちの可能性、自分たちの可能性を信じて邁進してまいりました。
現在当青年会議所は、入会歴3年未満の会員が半数を超え、経験値が不足している状況です。その様な状況だからこそ、青年らしい情熱を心に燃やし、自分たちがまちに対し、何ができるのか、どうすればまちがより良くなるのかを、真剣に考えなければなりません。会員一人ひとりが、まちの可能性を信じ、リーダーシップを発揮することで、当青年会議所は、まちの活性化に大きな役割を担う団体となることができるのです。そしてそのためには、会員間の相互理解を深め、会員全体が一丸となることが何よりも大切です。
会員同士が夢を語り、まちを語り、そこから生まれる団結力をもって、まちに良い変化を与える大きなうねりを生み出してまいります。
組織の基盤を固め会員の資質を向上させる運営
青年会議所の組織に欠かせないのが総務系の委員会です。一年間、我々の活動の基盤を支える要となります。
毎月必ず全会員が一堂に会する場である例会。この貴重な機会を、会員間の交流や自己啓発の機会として活かすことができるように、頭を悩ませながら工夫を凝らしたコンテンツにしていくことが総務系の委員会の挑戦であり醍醐味の一つです。本年は、例会という場において、委員会タイムや講師例会を活用し、会員が参加したくなる例会を開催してまいります。また、登壇の機会を利用し、会員の資質向上の場としてもしっかりと活用して、各例会の魅力を高めたいと考えております。
本年は、一年間創意工夫しながら例会運営に努め、例会から当青年会議所が勢いづくような活動をしてまいりたいと考えています。
会員全体で行う拡大活動及びリーダーシップを発揮できる人財の育成
青年会議所は、多くの仲間がいてこそ、地域により良い変化を与えることができます。そのため、ともに活動する仲間が増えることは、青年会議所運動をより効果的に行う上で、最重要事項の一つとなります。
当青年会議所では、近年、毎年多くの新入会員が入会しており、会員拡大の良い流れが続いています。しかし、その様な状況においても、卒会及び退会により、毎年の期首会員数は横ばいの状態が続いています。そのため、既存のやり方に囚われることなく、時代の変化に対応しながら、会員拡大のための新たな手法を模索し、実施していくことが重要です。
仮入会後においては、会員と交流をし、事業やボランティアに積極的に参加することで、自己の経験や成長に繋げて欲しいと考えています。魅力的な人材が入会し研鑽を積むことで、やがては下関にとどまらず、日本全国、または世界においてリーダーシップを発揮できる人財に育っていくようにサポートしてまいります。
まちに活気を与えるまつりの企画・運営
私たち下関市民の夏の恒例行事として、長く親しまれてきた馬関まつりは、本年で第47回を迎えます。昨年、馬関まつりは、4年ぶりに平家踊総踊り大会、朝鮮通信使行列再現も再開しフルパッケージの形で開催されました。二日間にわたり天候にも恵まれ、たくさんの人出で溢れかえり、新型コロナウイルス感染症が蔓延する以前のまつりの様子に戻ったことを実感しました。
一方で、ボランティア参加者の減少によるマンパワーの不足、各会場の場所が分断されているため他会場との一体感の創出に関しては、課題があると感じました。
本年は、JCパークが緑地化され、例年とは異なる条件での開催となるかもしれません。「市民祭」としての本質を尊重し、他会場と連携しながら、まちに活気を与え、人々に笑顔を咲かせることができる、まつりの企画、運営を目指します。
まちの未来を描き次世代に繋げていく
下関市では、現在、まちの姿が大きく変わるプロジェクトが進行しています。あるかぽーとにおいては、星野リゾートリゾナーレ下関が2025年秋にホテルを開業予定です。また、火の山においては、再編整備により昨年度より「光の山プロジェクト」が始まっており、今後観光客の増加が見込まれます。
一方で、人口減少、高齢化の問題は、依然としてまちの抱える大きな課題の一つなのです。下関市から2022年3月に出された、「下関市都市計画マスタープラン」によると、2040年に、下関市の人口は約19.6万人まで減少し、その内の4割近い人が高齢者となります。
交流人口対策は練られている一方で、定住人口対策が進んでいない中、われわれは、下関市の魅力を見出し、内外に発信していく必要があります。三方を海で囲まれ、豊かな自然に恵まれた下関市は、歴史、食、文化等、市民にとっては当たり前だと感じている隠れた魅力が数多く存在します。市民がまちの魅力を認識することで、まちに対する愛着が高まり、市外への人口流出の減少やUターン就職者の増加に繋がると考えます。そして、市民一人ひとりが新たなまちの魅力を知り、発信していくことで、下関市に興味を持ち、訪れてみたい、住んでみたいと思う人が増えていくことに繋がると私は信じています。
まちの魅力というものは、まちが持つ資源等だけではありません。地方と都市部のまちを比べて、一番大きく異なるのは、職業や教育、イベントの機会の数だと考えます。大きなまちであればあるほど、雇用や創業の機会、多様な教育の機会、多彩な体験の機会があるといえるでしょう。その差を急に埋めることはできません。しかし、そうした機会を一つでも増やすことができるように、教育関連のイベントやワークショップなど、まずは次世代のための機会創出にアプローチしていきたいと思います。
国際連携の強化
JCI KOREA BUSANと一般社団法人福岡青年会議所とのトリオJCの関係は、半世紀を超えて続いており、三団体の連携は国内でも珍しい取組みです。毎年、TRIO会議の名を冠する国際会議を開き、活発に往来を続ける我々の友情は、長年積み重ねられてきた相互交流に基づくものです。本年も引き続き、三団体間の良好な関係を継続していきたいと考えています。
そして、本年は、日韓国交正常化前の1964年にJCI KOREA BUSANとの姉妹締結がされてから60周年という記念すべき年です。姉妹締結以降、積極的な民間交流を続けており、両青年会議所にとって貴重な国際交流の機会となっております。60周年という節目の年になるため、お互いに意見交換をしながら、両青年会議所間の交流が両都市の市民間の交流へと発展していくような企画を実施したいと考えています。
また、世界中に広がるJCIのネットワークを活かし、他の国のJCIとの交流の機会も模索し、当青年会議所の国際的な視野の拡大にも努めてまいりたいと考えております。
関門エリアの魅力を発信する
昨年、下関市、北九州市の両市長が12年ぶりに会談を行い、関門新連携を掲げて、ジップラインの設置をはじめとする様々な取り組みを協力しておこなっていくことを発表しました。関門エリアの連携は民間においても、まちの活性化という面からも重要な要素のひとつです。ここ数年、下関北九州道路に関する事業を展開してきた当青年会議所としましても、この機会に関門エリアの景観等、地域の魅力を発信できるような企画を実施していきたいと考えています。また、友好JCである一般社団法人北九州青年会議所とは、近年、その連携を強化しており、本年も引き続き良い関係での交流を進めて行きたいと考えています。
中国地区球技大会の主管
4年前、新型コロナウイルス感染症の影響で、我々が主管する予定であった中国地区球技大会が中止となりました。しかし本年、新たに、中国地区球技大会の主管をすることとなりました。このたびの球技大会においては、中国地区協議会管内の各ブロック協議会から勝ち上がってきた代表チームが、ますますその力を存分に発揮できるよう、快適に野球をおこなえる環境を調え、お越しいただいたチームの皆様に、下関市の魅力を少しでも知っていただけるように、企画、運営してまいります。
結びに
私たちは、満40歳までという限られた時間の中で、まちをより良くしたいと願い活動しています。その限りある時間をより有効に使うために、本年は夢を語り、まちを語る機会を積極的に増やしていき、我々会員の考え方の幅を広げ、各々が持っている良さを引き出していく年にしたいと考えています。
昨年、当青年会議所は創立70周年を迎えました。その一つの区切りを経て、本年は新たな第一歩を踏み出す重要な年となります。
入会してからこれまで、私が当青年会議所で学んできたことの全てを注ぎ込み、まちと本気で向き合う年にしたいと考えています。
一人ひとりの小さな行動の積み重ねで、まちは必ず変わる。私たち会員一同、個々が持つ資質を最大限に活かし、かつ協調し、この一年間を楽しみ抜いてまいります。
一般社団法人下関青年会議所
第71代理事長 濵﨑 博光